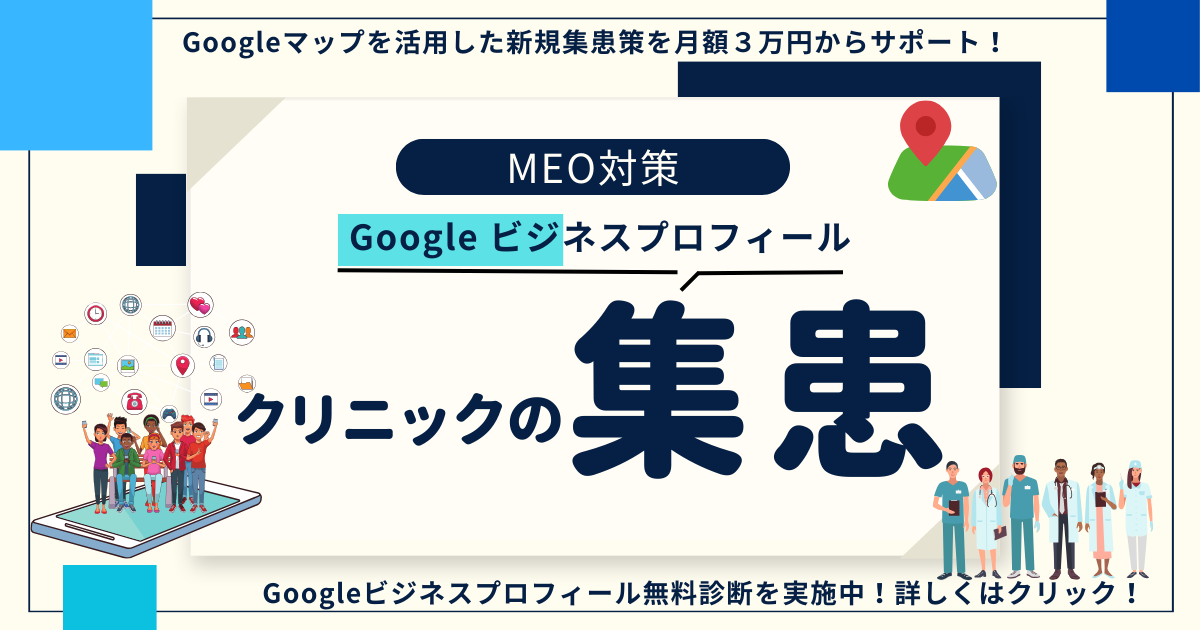・厚生労働省は昨年、医療法(医療広告ガイドライン)に違反するウェブサイトを1000件以上確認し、改善を求めた。虚偽や誤解を招く広告が横行し、患者の選択を誤らせ健康被害につながる危険性があるため、監視体制を強化している。
・東京都内の30代女性は美容医療クリニックのサイトで「痩せる注射」と宣伝されていた施術を複数回受けたが効果はなく、高熱の副作用にも苦しんだ。返金を求めても拒否され「だまされたようで悔しい」と語った。
・医療法は「ビフォー・アフター写真」や根拠のない「満足度表示」、体験談などの掲載を禁止している。2018年6月の法改正で医療機関のサイトや医師のSNS発信も規制対象となった。
・厚労省はネットパトロールを実施し、違反が疑われる表現を検索や通報で把握。2023年度は1098サイトで計6328か所の違反が見つかり、歯科と美容に集中していた。
・改善要請に応じない医療機関には自治体が立ち入り検査や行政指導を行い、悪質な場合は刑事告発もある。ただし自治体の対応には差があり、厳格な対応をためらうケースも多い。
・厚労省は自治体の負担軽減のために指導マニュアルを整備し、連携を呼びかけている。今年度は監視を一層強化する方針を示した。
・医療人権団体の専門家は、国による具体的な指導事例の共有が必要と指摘。さらに患者自身が広告の真偽を見極める力=ヘルスリテラシーを高めることも不可欠だとしている。